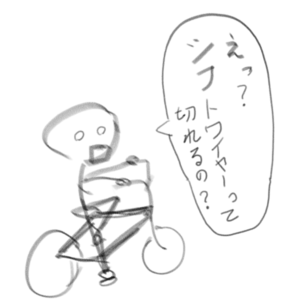さて。先日からいつくかのエントリで書いておりましたが、アラヤ (araya) CXG 2018年モデル(サイズ:500mm) が納車されてから2ヶ月たち、走行距離も1000キロに達したのでレビューしてみようと思います。
とはいえ、今まで乗った自転車なんてママチャリとミヤタのEigerという名前のMTBルック車と、昔の名称不明のランドナーしか乗ったことはないので正直当てにあるかどうかは怪しいですけどね:-P
どんな自転車?
日本の自転車メーカー「ARAYA(アラヤ)」が作っている自転車。旅行用の自転車が欲しくて探すと必ず候補に挙がるメーカーだけれど、ロードバイクを探すと選択しに上がることはあまりないんじゃないかと思うのだけれどどうでしょう。
その中でもCXG(CX Gravel)は、グラベルロードというジャンルのモデルとなります。舗装路に加え、砂利道の走行も考え、少し太めのタイヤ、丈夫な車体、ディスクブレーキを装備しています。
2017年までのモデルまではフロントフォークがカーボンだったのですが、2018年からフォークまでクロモリ(鉄)になりました。個人的にはこれが決め手となり、購入に至りました。正直カーボンはシルエットが好きじゃないのです。軽さは非常に魅力的ですが、まぁ、フレームがクロモリなのでフォークだけカーボンにしてもな、と思っていたので。
ハンドルが下広がりのフレアドロップになったのも相まって、完全にツーリング車になったというイメージですね。ツーリングなのかレーサーなのか、という中途半端さがなくなり、直球ストレートなツーリング車になりました。
乗ってみてのレビュー

乗り心地は悪くない
まず、乗り心地が思ったより遙かにいいです。
クロモリとは言っても、ミッドサイズなのでガチガチであることも覚悟していたのですが、そのようなことはありませんでした。
35Cの太めなタイヤと柔らかめのシートのおかげか、大きな入力もある程度緩和してくれるので、乗り心地は悪くありません。これに関しては、重さもメリットになっているのかもしれません。(軽いと跳ねちゃいますからね)。ちなみに上の写真の状態からフロントバッグ抜きで実測16.9kgです。重いパーツを付けまくっているから仕方ないですが、ロードバイクと違って重いパーツを付けても心が痛まないのはこの自転車の利点だと思うのですがどうでしょうか。
フレームもしっかりしているので、不意に小石などを踏んだ際の横方向のよれも少なく、安心感があります。いつまでも振動が残るということもなく、快適です。
いまのところ一度に50キロ程度しか乗っていないのでもっと長距離走った時どうなるかは不明ですが、体へのダメージが少ないので、100キロ程度はイケる感はあります。それ以上は不明です。体力的に自信がありません(;´Д`)
いくらでも走れそうには思えますが…
それなりのスピード
平地に関しては特に重さを感じることはありません。それなりに(自分の足の場合、原付の最高時速程度かな)速度も出ます。
向かい風であっても下ハンを握ることで正面からの投影面積を少なくすればスピードの維持も容易です。さすがはドロップハンドルです。
しかし、上り坂になるとやはり重い。少々荷物を積んでいると一番軽いギア(前34-後32)を選択することも少なくありません。もっと軽いギアが欲しくなったことは今のところありませんが、坂がきつかったり、長かったり、荷物が多ければ欲しくなるかもしれません。
このへんは一度近所のスキー場まで乗ってみてみようと思います。
それなりの走破性
ママチャリ程度のタイヤの太さがありますので、砂利道や多少荒れた道なども突っ込んでいけます。なので、ちょっといつもと違う道を探検してみるとか、ちょっとした冒険心を満たしてくれます。
拡張性はポテンシャル
多数のダボ穴があるため、キャリアを付ければ7自転車としてはトップクラスの積載を誇ると思いますが、自分の場合はとくに日本一周とかするわけでもないので、フロントはサイドバックが付けられない小さいもの(日東のM-18)、リアキャリアは普通の(Super Tourist DX Tubular Rack )という構成にしております。
近所のスーパーに買い出しに行く場合程度であれば、これで十分実用になります。
積載以外にも、フェンダーを付けたり、ライト、カメラなどのアクセサリーを付けたり、多数のダボ穴は常に味方です。これ網現代版のランドナーなんじゃないかな?
トゥークリップを付けるとフェンダーに干渉するのは残念
この自転車の性格上、ビンディングはなんとなく違う気がして、(お金がないのもあるけれど)ハーフトゥークリップを装着していますが、ハンドルを切るとフェンダーに干渉してしまいます。あと1センチホイールベースが長ければ大丈夫だったんじゃないかと思うのですが、ざんねん。慣れるしかないですね。

やっぱり前傾姿勢つらいです
ロードバイクと比べたらアップライトな姿勢、といわれますが、それでもある程度の前傾姿勢になるので、しばらく乗っていると肩、首がつらくなってきます。
慣れかな!(`・ω・´)
まとめ:楽しい
ロングライドも、ちょい乗りも、荷物が多くても、ちょっと荒れた道も、これ一台でこなせるはず。ガチな用途があれば、ガチな自転車を用意すれば良いけれど、それなりであれば、これでOK。自転車に不安なところがないから、安心して楽しめます。
別にこの自転車に限ったことではないけれど、人力でこれだけ移動することができるというのはもう単純にそれだけで楽しいですね。
まぁ、スペック的には車重が重いとか、スルーアクセルじゃないとか、やっぱり重いとかありますが、乗ってるとどうでも良くなってきます。人と競争するような自転車でもないですからね。
加えて、この自転車なら快適性、走破性、拡張性において高いレベルを持っているので、末永く楽しめそうです。